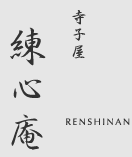2015/02/23 з”ІйҮҺе–„зҙҖе…Ҳз”ҹ д»Ӣиӯ·иә«дҪ“и«–

иЁҳпјҡж—Ҙй«ҳжҳҺ
гҖҖжӯҰиЎ“з ”з©¶е®¶гҒ®з”ІйҮҺе–„зҙҖе…Ҳз”ҹгӮ’гҒҠиҝҺгҒҲгҒ—гҒҰгҖҒд»Ӣиӯ·зҸҫе ҙгҒ§гҒ®иә«дҪ“гҒ®дҪҝгҒ„ж–№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ®и¬ӣеә§гҒҢй–ӢгҒӢгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҖи¬ӣеә§гҒҜз”ІйҮҺе…Ҳз”ҹгҒЁз·ҙеҝғеәөдё»е®°гҒ®йҮҲеҫ№е®—гҒЁгҒ®иә«дҪ“и«–и«Үзҫ©гҒӢгӮүгҒҜгҒҳгҒҫгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгғҲгғ”гғғгӮҜгҒҜеӨҡеІҗгҒ«гӮҸгҒҹгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒ“гҒ“гҒ«гҒІгҒЁгҒӨгӮ’жҢҷгҒ’гӮҢгҒ°гҖҢеҝғгҒЁдҪ“гҒЁгҒ®еҜҶжҺҘгҒӘгҒӨгҒӘгҒҢгӮҠгҖҚгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖӮ
гҖҖгҒ„гҒҫгҒ®гӮ№гғқгғјгғ„з•ҢгҒ§гҒҜгҖҒгғҲгғғгғ—гӮўгӮ№гғӘгғјгғҲгҒ«гҒӘгӮӢгҒ»гҒ©гғ•гӮЈгӮёгӮ«гғ«гҒӘгғҲгғ¬гғјгғӢгғігӮ°гҒЁгҒҜеҲҘгҒ«гҖҒгғЎгғігӮҝгғ«гғҲгғ¬гғјгғӢгғігӮ°гӮӮиЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ§гӮӮдәәй–“гҒ®еҝғгҒЁдҪ“гҒҜгҖҒгҒ•гҒҸгҒЈгҒЁеҲҮгӮҠеҲҶгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮз·ҠејөгӮ„жҒҗжҖ–гҒӘгҒ©гҖҒеҝғгҒ®еӢ•жҸәгҒҜгҖҒеҚіеә§гҒ«иә«дҪ“гҒ«гҒӮгӮүгӮҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮйҖҶгҒ«гҖҒиә«дҪ“гҒ®гӮігғігғҲгғӯгғјгғ«гӮ’йҖҡгҒҳгҒҰеҝғгҒ®иӘҝж•ҙгӮ’иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгӮӮеҸҜиғҪгҒӘгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҖз”ІйҮҺе…Ҳз”ҹгҒҢиҰӢгҒӣгҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒЈгҒҹгҒ®гҒҜгҖҒгҖҢй·№еҸ–гҒ®жүӢгҖҚгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢгҒӢгҒҹгҒЎгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮгҒҫгҒҡдёЎжүӢгҒ®иҰӘжҢҮгҒЁдәәе·®гҒ—жҢҮгҒЁе°ҸжҢҮгӮ’еҗҲгӮҸгҒӣгӮӢгҖӮгҒӨгҒҺгҒ«е·ҰеҸігҒ®жүӢгҒ®и–¬жҢҮгӮ’дәӨе·®гҒ•гҒӣгҖҒгҒҹгҒҢгҒ„гҒ«еј•гҒЈејөгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®еҪўгҒ«жүӢгӮ’зө„гӮҖгҒЁгҖҒиҮӘ然гҒЁжЁӘйҡ”иҶңгҒҢдёӢгҒҢгӮҠгҖҒе‘јеҗёгҒҢиҗҪгҒЎзқҖгҒҚгҖҒзӘҒ然гҒ®дёҖеӨ§дәӢгҒ«гҒ•гҒ„гҒ—гҒҰгӮӮгӮўгӮ¬гҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ“гҒЁгҒӘгҒҸеҶ·йқҷгҒ«еҜҫеҝңгҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒ гҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮ
В
гҖҖгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒй•·гҒ„е№ҙжңҲгҒ«жёЎгҒЈгҒҰеӨҡгҒҸгҒ®е…ҲдәәйҒ”гҒҢзҷәиҰӢгғ»й–ӢзҷәгҒ—гҒҰгҒҚгҒҹжҠҖжі•гҒ«гҒҜгҖҒеҝғиә«гҒ®гғ‘гғ•гӮ©гғјгғһгғігӮ№гӮ’жңҖеӨ§еҢ–гҒҷгӮӢзҹҘжҒөгҒҢи©°гҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ§гҒҷгҒҢгҒқгӮҢгӮ’зҹҘгӮүгҒӘгҒ„иҝ‘д»ЈдәәгҒҜгҖҒиә«дҪ“гҒ®гҒӘгҒӢгҒ®еҠӣгҒ®еӨ§йғЁеҲҶгӮ’зң гӮүгҒӣгҒҹгҒҫгҒҫйҒҺгҒ”гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°з§ҒгҒҹгҒЎгҒҜгҒөгҒ гӮ“жүӢгӮ„и…•гӮ’иҮӘз”ұгҒ«дҪҝгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒӮгҒҫгӮҠгҒ«дҫҝеҲ©гҒҷгҒҺгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒқгҒ®дҪҝз”ЁгҒ«ж…ЈгӮҢгҒҚгҒЈгҒҰгҖҒдҪ•еҖҚгӮӮгҒ®еҠӣгӮ’з§ҳгӮҒгҒҰгҒ„гӮӢиғҢзӯӢгӮ„и„ҡгӮ’жҙ»гҒӢгҒҷгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒқгҒ—гҒҰи„ігҒҜгҖҒгҒӘгҒ«гӮ’гҒҷгӮӢгҒ«гӮӮжүӢгӮ„и…•гҒ®еҠӣгҒ«й јгӮҚгҒҶгҒЁгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮжүӢгҒЁгӮәгғ–гӮәгғ–гҒ®й–ўдҝӮгӮ’гҒЁгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶи„ігӮ’гҖҒз”ІйҮҺе…Ҳз”ҹгҒҜгҖҢгғҗгӮ«зӨҫй•·гҖҚгҒЁе‘јгҒігҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҖе…Ҳз”ҹгҒ„гӮҸгҒҸгҖҒгҖҢгҒ“гҒ®гғҗгӮ«зӨҫй•·гҒҢгҖҒгҒ—гӮғгҒ—гӮғгӮҠеҮәгҒҰгҒҸгӮӢжүӢгҒ°гҒӢгӮҠгӮ’и©•дҫЎгҒ—гҒҰгҖҒеҸЈж•°гҒҜе°‘гҒӘгҒ„гҒ‘гӮҢгҒ©иғҪеҠӣгҒ®гҒӮгӮӢиғҢзӯӢгӮ„и„ҡгӮ’зӘ“йҡӣгҒ«иҝҪгҒ„гӮ„гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮ“гҒ§гҒҷгҖӮгҖҚгҒ гҒӢгӮүгҖҒиә«дҪ“е…ЁдҪ“гҒ®еҠӣгӮ’еј•гҒҚеҮәгҒқгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢгҒӘгӮүгҖҒгҒ“гҒ®еҮәгҒ—гӮғгҒ°гӮҠгҒӘжүӢгӮ’жҠ‘гҒҲгҒҰгҒҠгҒҸеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ“гҒ§гҖҒгҖҢж—Ӣж®өгҒ®жүӢгҖҚгҒ§гҒҷгҖӮи©ігҒ—гҒҸгҒҜзңҒгҒҚгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜдә”жҢҮгӮ’зӢ¬зү№гҒ®гҒӢгҒҹгҒЎгҒ«еӣәе®ҡгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒеҠӣгӮ’жӢ®жҠ—гҒ•гҒӣгҒҰжүӢгҒ®дҪҷиЁҲгҒӘеӢ•гҒҚгӮ’гҒӮгҒҲгҒҰжҠ‘гҒҲгҒ“гҒҝгҖҒиә«дҪ“гҒ®д»–гҒ®йғЁдҪҚгҒ®гҒЎгҒӢгӮүгӮ’еј•гҒҚеҮәгҒҷгҒҹгӮҒгҒ®гҒӢгҒҹгҒЎгҒ§гҒҷгҖӮзӣёжүӢгҒ«жүӢйҰ–гӮ’гҒӨгҒӢгӮ“гҒ§гӮӮгӮүгҒ„з«ӢгҒЎдёҠгҒҢгӮүгҒӣгӮӢгҒЁгҒҚгҒ«гӮӮгҖҒгҒ“гҒ®ж—Ӣж®өгҒ®жүӢгӮ’зө„гӮҖгҒЁи…•гҒ®еҠӣгҒ§з„ЎзҗҶгҒ«еј•гҒЈејөгӮүгҒҡгҒ«иә«дҪ“е…ЁдҪ“гӮ’дҪҝгҒҶгҒҹгӮҒгҖҒз°ЎеҚҳгҒ«зӣёжүӢгӮ’з«ӢгҒЎдёҠгҒҢгӮүгҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҖгғҲгғјгӮҜгҒҜгҒқгҒ®еҫҢгҖҒеҸӮеҠ иҖ…гҒ®зҡҶгҒ•гҒҫгҒ«гӮҲгӮӢе®ҹжҠҖгҒёгҒЁжөҒгӮҢиҫјгҒҝгҖҒз·ҙеҝғеәөгҒҜд»Ӣиӯ·иә«дҪ“и«–гҒ®е®ҹи·өз ”з©¶гҒ®е ҙгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҖд»°иҮҘдҪҚгҒӢгӮүеә§дҪҚгҒёгҒ®иө·гҒҚгҒӮгҒҢгӮҠгҒ®д»ӢеҠ©гҖҒжӨ…еӯҗгҒӢгӮүгҒ®з«ӢгҒЎдёҠгҒҢгӮҠгӮ„жӨ…еӯҗгҒёгҒ®и…°гҒӢгҒ‘гҒ®д»ӢеҠ©гҖҒжӯ©иЎҢд»ӢеҠ©гҖҒгғҷгғғгғүдёҠгҒ§гҒ®гҒҠгӮҖгҒӨдәӨжҸӣжҷӮгҒ®д»Ӣиӯ·иҖ…гҒ®е§ҝеӢўгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒӘгҒ©гҖҒеҸӮеҠ иҖ…гҒ®зҡҶгҒ•гҒҫгҒӢгӮүгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘиіӘе•ҸгҒҢгҒӮгҒҢгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҖҢгҒӘгҒӢгҒӘгҒӢгғҷгғғгғүгҒӢгӮүиө·гҒҚдёҠгҒҢгӮҚгҒҶгҒЁгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгҒӘгҒ„еҲ©з”ЁиҖ…гҒ«гҒҹгҒ„гҒ—гҒҰгҖҒгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«еЈ°гӮ’гҒӢгҒ‘гӮҢгҒ°гҒ„гҒ„гҒӢгҖҚгҒӘгҒ©гҖҒиіӘе•ҸгҒҜд»Ӣиӯ·гҒ®иә«дҪ“жҠҖжі•гҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгӮігғҹгғҘгғӢгӮұгғјгӮ·гғ§гғігҒ®д»•ж–№гҒ«гҒҫгҒ§гҒҠгӮҲгҒігҒҫгҒҷгҖӮз”ІйҮҺе…Ҳз”ҹгҒҜгҖҒгҒқгӮҢгҒ«еҚіеә§гҒ«гҖҒгҒЁгҒҚгҒ«иҖғгҒҲгҒӘгҒҢгӮүгҖҒиә«дҪ“гҒЁеҝғгҒ®еғҚгҒӢгҒӣгҒӢгҒҹгӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
В
гҖҖдәҲе®ҡгӮ’30еҲҶгӮӘгғјгғҗгғјгҒ—гҒҰгҒ®зөӮдәҶеҫҢгӮӮгҖҒгҒӘгҒҠгҒ»гҒЁгҒјгӮҠгҒ®еҶ·гӮҒгҒӘгҒ„еҸӮеҠ иҖ…гҒЁз·ҙеҝғеәөгӮ№гӮҝгғғгғ•гҒҢе…Ҳз”ҹгҒ®гҒЁгҒ“гӮҚгҒёиіӘе•ҸгҒ«жҠјгҒ—гҒӢгҒ‘гҖҒиЎ“гӮ’дҪ“йЁ“гҒ•гҒӣгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҖҢд»Ӣиӯ·гӮ’гҒЁгҒҠгҒ—гҒҰдҪ“гӮ’йҚӣгҒҲгӮӢгғ»иӘҝгҒҲгӮӢгҖҚгҒҹгӮҒгҒ®гғ’гғігғҲгӮ’гҒҹгҒҸгҒ•гӮ“гҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҖҒеҸӮеҠ иҖ…гҒ®гҒҝгҒӘгҒ•гҒҫгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«иә«дҪ“йҒӢз”ЁгҒ®еҘҘж·ұгҒ•гҖҒгҒқгҒ—гҒҰйқўзҷҪгҒ•гӮ’гҖҒиә«гӮ’гӮӮгҒЈгҒҰзҹҘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҹеҚҲеҫҢгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮз”ІйҮҺе…Ҳз”ҹгҖҒгҒӮгӮҠгҒҢгҒЁгҒҶгҒ”гҒ–гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ