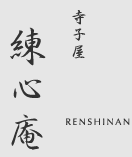2015/09/29 9月期初歩からの宗教学講座
記:日高明
イスラム、神道、ヒンドゥー教と、世界の諸宗教を巡っています「初歩からの宗教学講座」は、いよいよ仏教にさしかかりました!
今回は、「ヒンドゥー文化圏の宗教」と題して、ヒンドゥー教の基盤となった古来のヒンドゥー文化圏の宗教と、2500年前に同時多発的に起こってきた様々な新しい思潮、そしてそのなかのひとつである最初期の仏教へとお話が進められました。ヒンドゥー文化圏の宗教と対比することで、仏教の特徴もはっきりと見えてきます。
ヒンドゥー教は4世紀頃に成りますが、その母体となったヒンドゥー文化の起源とえいば、はるか紀元前数千年にまで遡ります。
================================
人類が抱え込む“過剰”なエネルギー
================================
人類は誕生以来、自分のなかに抱え込んだ過剰なエネルギーといかに付き合うかということを一大テーマにしてきました。人間以外の動物は、無駄なことはしません。必要なだけ食料を捕り、子孫を残して死んでいく。でも人間は、ただ生きて死ぬということができない。シンプルな生命維持活動から逸脱して、自然の循環から外れる過剰さを持つ。必要以上に貯めこんだり、必要もないのに浪費したりする。恐れから争い、愛着から争い、偏見から争い、争いのために争いもする。作っては壊し、壊しては作るといった具合に、人間以外の動物から見れば、無駄なことばかりでしょう。この過剰さゆえに人間は固有の喜びを味わい、またこの過剰さゆえに人間は苦しみを背負うことになりました。
ヒンドゥー文化圏の宗教は、長い長い歴史をとおして、そうした過剰なエネルギーを扱うための身体技法や哲学を蓄積し、彫琢してきたのです。それは強烈な有の思想でした。
================================
カルマ(業)と輪廻からの解脱
================================
ヒンドゥー文化圏の宗教においては、私たちの思いや言葉や行為は、発せられ行われた時だけで終わるものではありません。それが善いものであれば善いカルマ(業)として、悪いものであれば悪いカルマとして、蓄積されていきます。どこに蓄積されるかというと、前世・現世・来世を輪廻する本体としての私、アートマン(我)に蓄積されます。
行った行為は、その場で終わらない!幾世も幾世も積もり積もって、また次の行先が決められます。
しかしどこに生じても苦しみがつきまとうから、この輪廻を脱しなければならない。ヒンドゥー文化圏の宗教でもいろいろと体系が分かれるところですが、一番メジャーな脱出方法は、宇宙の意志と合体すること。この宇宙の意志はブラフマン(梵)と呼ばれます。梵と我が一体になることによって、輪廻から解脱することができる。そのように考えられました。
生死や時空をつらぬいて、「すべてはある!」と考える圧倒的な有の哲学……。宗教を「個人のこころの問題」にすぼめて無難に理解してしまおうとする現代的な宗教観・人間観など一飲にされてしまいそうな、壮大な存在論です。
================================
アンチ・バラモン教としての側面
================================
しかしこのような伝統的なヒンドゥー文化圏の宗教、とくに特権的な司祭階級であるバラモンを中心としたバラモン教へのカウンターとして、新しいムーブメントが起こります。
宗教儀式を重視し、カースト制を維持するバラモン教に対して、2500年前、異議を唱える人々が現れました。彼らはバラモン階級の出身ではない出家者として、「シュラマナ(沙門)」と呼ばれます。これらのシュラマナたちが、のちにジャイナ教、アージーヴィカ教、ローカーヤタ教と呼ばれる宗教を形成することになります。そして、若きゴータマ・シッダルタ(のちのブッダ)もまたシュラマナのひとりであり、仏教はアンチ・バラモン教というニュームーブメントのなかにあったわけです。仏教も当時にあっては新宗教だったのですね。
================================
“有”と“無”、それぞれの思想
================================
さて、仏教は、古来のヒンドゥー文化圏の宗教が有の思想であるのとは逆に、無の思想です。
不滅の存在などない、と説くのが仏教の大きな特徴になります。あらゆるものは関係性で成り立っている、それ自身だけで存在するものはない、変化せず永続するものない、と考えます。ずっと変わらないアートマンを説く伝統的なヒンドゥー文化圏の宗教とは、まったく異質な教えです。
圧倒的な有の宗教地層のなかで、仏教は、異物のように無の思想、無我の立場を展開することになりました。
なぜ仏教は、無我の立場に立ったのか?
それは、自分というものにしがみつけば、苦しみの連鎖から逃れられないから。自分への執着を手放すために、我というものはないんですよ、と説く。その大本は、この苦難に満ちた人生をいかに生ききって死にきるか、というところにあります。
テーラーヴァーダ(上座部)とマハーヤーナ(大乗)という仏教の二大派の共通基盤である「縁起」「中道」「無常」とともに、この「無我」についても、また次回以降にうかがいたいと思います。
================================
愚鈍第一と言われた弟子
================================
もうひとつ印象に残ったことを。
ブッダの弟子の一人であるチューラパンタカは、他の有名な弟子方が「智慧第一」や「神通第一」などと言われるなか、ひとり不名誉にも「愚鈍第一」と言われています。お経は覚えられず、自分の名前さえ覚えていられない人だったそうです。
そうしてだれからも見放された彼に、ブッダは箒を与え、「塵を払わん、垢を落とさん」と唱えながら掃除をしなさいと教えます。
毎日毎日、一心に掃除を行い続けた結果、ついにチューラパンタカは悟りに至ったということでした。
日本に浄土仏教の礎を固めた法然は、「浄土宗の人は愚者になりて往生す」と言ったとされます。
自分自身の名前さえ捨ててしまうようなチューラパンタカの「愚鈍さ」や、法然の言う「愚者」の愚かさは、自分への執着を離れ、ただひとつの行いになりきる純一さでもあるでしょう。「過剰さ」に振り回され続ける私にとっては、そのような愚かさは、無我ということとなんら変わらないように思えました。