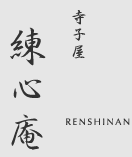2015/10/21 10月期 初歩からの宗教学講座
記:日高明
前回に引き続き「ヒンドゥー文化圏の宗教」ということで、現代のヒンドゥー教のもとになった古層の宗教と、またそこから派生してきた初期の仏教を概説していただきました。
================================
ヒンドゥー文化圏の神々
================================
ヒンドゥー教では、中心となる神が移り変わってきています。ずっと昔は火の神アグニ、その次にブラフマン、というふうに。こういうのをカセノシイズム(交替神教)と言うそうです。
神話においては、この世界を創造したのはブラフマンということになっています。しかし「創造神=最高神」にならないのがヒンドゥーの面白いところで、ブラフマンは唯一にして絶対の神というわけではない。現在の主流は破壊の神シヴァです。
このブラフマンには顔が四つあります。なぜかというと、ブラフマンは妻であるサラスヴァティが好きで好きでたまらない、いつでも妻を見ていたくて、顔が四つになってしまったのです。どの地域のものであれ、神話には現代人からすると突拍子もないと感じられるエピソードがあるものですが、しかしこのブラフマンの四面の由来、もうちょっとなんとかならなかったのか。
「顔四つにしちゃいました!」という神話的な「斜め上」感のなかに、「好きすぎて」という素朴さを盛り込んでいるところに、カーマ(性愛)を人生の重要な目的と見なすヒンドゥー文化の神話っぽさがあると言えばたしかにそうかもしれません……。
妻がらみで言えば、破壊の神シヴァは、妻であるパールヴァティの入浴を覗かせろと言って息子のガネーシャと争って首を跳ね飛ばしてしまう。争いの理由も理由ですが、こちらはさすがに破壊神、荒ぶっています。ちょっと荒ぶりすぎちゃったなぁということで、新しい首をつけてあげるのはいいのですが、つけられたのはそこに通りかかった象の首でした。なんともアバウトです。
しかしこのシヴァ神、別の奥さんであるカーリー(戦いの神)の喜びダンスで地震が起きそうになり、地面を踏み鳴らすカーリーの足の下に自分が入ることでショックを和らげようとしたりと、荒ぶる神に似つかわしくない扱いを受けてもいます。喜び踊る妻に踏みつけられる破壊神。破壊の神なのに身を挺して大地を守っちゃうんですから、ちょっと親近感沸いてきますね。
こうした神々の物語にしても、またその神々の描かれ方にしても、現代の私たちとはやはり感性が異なる、しかしそれだけに魅了されるヒンドゥー文化です。
このような神々を描く叙事詩のほか、ヒンドゥー文化は信仰と一体となった哲学・思想を特徴として持っています。
大きく分けると、アースティカ(「有る」とする人たち)とナースティカ(「無い」とする人たち)に分けられます。
アースティカのほうが正統派で、彼らは「すべては有る、そしてその基礎には神がある」と考えます。仏教は、逆に、そのような神を認めず、すべては関係性で成り立つと考える立場ですから、ナースティカの側になります。ナースティカは異端になります。ヒンドゥー教の人からすると、仏教もジャイナ教もヒンドゥー教のなかの異端派ということになるわけです。
================================
ブッダの悟り(縁起、中道、智慧と慈悲)
================================
さてこの初期の仏教は、出家者中心の教えです。出家は、生きる上での苦悩を解決するための道でした。
ブッダが悟り、出家者たちに伝えようとした内容は、縁起、中道、智慧と慈悲、などであるとされています。
ブッダは徹底的に分析的な手法でもって苦の原因を明らかにしていきました。苦悩を縁起の視点で捉えると、それがなんらかの原因によって生じた結果だと分かります。
その原因とは、突き詰めれば、自分の執着です。すべては移ろい変化していくにもかかわらず、それを認めることができず、執着してしまうがために、苦しみが生じてしまう。極端な話、執着をゼロにすれば、苦悩もゼロになるはずです。
この執着は、自分の心と身体を点検していなければ、すぐに偏り、膨らみ、暴れだす。
だから心と身体を調えることによって、苦しみの連鎖を安らぎの落ち着けていく。このように考えるのが、メインラインの仏教です。
どんなに素晴らしい考えも、どんなに素晴らしい行為も、必ず偏っていく。偏ったら、具合が悪くなる。
仏教における正しさとは、「偏らないこと=中道」です。
思考や行為そのものの善悪が問題とされるのではなく、偏った思考、偏った行為が問題とされるのです。
とはいえ、まったく偏らずに考え、行為するのは難しいことです。私たちはいつも、自分の都合で物事を見ています。
好きな人ならば怒った顔さえ可愛らしく見え、嫌いな人の笑顔には下心を読み込んでしまう。嬉しいことがあれば景色も目に鮮やかに映り、悩みごとがあれば何も目に入らない。
ありのままには見ることができません。あらゆるものを自分の都合のフィルターを通して見てしまう。
こうした認知の歪みから、苦しみが生じることになります。
自分の都合を通さずに、物事をきちっとあるがままに見ることが、仏教の言う「智慧」です。
また、自分の都合を通さないということは、他者を自分と同じように大事にするということであり、その慈しみ憐れむ心を「慈悲」と言います。
世界中の仏教は、お光とお花でお荘厳します。光は智慧を、お花は慈悲を表します。
このような、縁起、中道、智慧・慈悲が、ブッダの悟りの中核にあったとのことです。