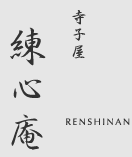2016/01/22 1月期 初歩からの宗教学講座
1月22日に行われた「初歩からの宗教学講座」のリポートです。
記:一ノ瀬かおる
2016年最初の「初歩からの宗教学講座」では、『観無量寿経』を学びました。
『観無量寿経』とは「王舎城の悲劇」をベースとした経典。「王舎城の悲劇」とは、マガダ国の王族を巡る物語です。マガダの王ビンビサーラ(頻婆娑羅)と妃のヴァイデーヒー(韋提希)の間には子どもがおらず、二人は「三年後にある仙人が死に、その生まれ変わりが自分たちの子どもとなる」という占いの言葉にすがります。しかし頻婆娑羅王は、その時を待ちきれず仙人を殺してしまいます。仙人は復讐の言葉を残して死んでいきました。その後、息子アジャータシャトル(阿闍世)が生まれますが、頻婆娑羅王は仙人の復讐の言葉が頭を離れず、自分はいつか息子に殺されるのではないだろうかという怖れにとらわれ、物心つかない阿闍世を殺そうとします。ですが、自分の行為を思い直した王は、阿闍世を後継者として大事に育てます。何も知らぬまま阿闍世は青年になりますが、ある日、仏弟子のデーヴァダッタ(提婆達多)から自身の出生の秘密を聞いてしまうのです。阿闍世は怒り、自らの父と、父をかばう韋提希を幽閉します。その後、頻婆娑羅王は死に、韋提希は苦しみにとらわれます。
頻婆娑羅王と韋提希が犯した罪は、業となって彼らに押し寄せました。その業の体現者となったのが阿闍世であり、その業はマガダ王国が背負う悲劇の起点となりました。結果、間接的とはいえ阿闍世は父親を死に追いやり、阿闍世自身も、後に自分の子どもに殺されたとも言われます。マガダ王国は、この後五代にわたり子が親を殺す構図が続きました。このような悲劇の中で、仏陀が、苦悩する韋提希にむけて説いたものが『観無量寿経』となるそうです。
『観無量寿経』では、瞑想法が説かれます。西に沈む太陽を見て、極楽浄土を思う修行〈日想観〉などはとても有名です。夕陽の先に異界を描き、大きい大きい物語に身を委ねる。自分の手に余る苦悩を、自分の手の及ばないものに預ける。マガダ王国の悲劇の終点は、もしかしたらそのような場面なのかもしれません。
今回の講座では、阿闍世の持つ強い感情・コンプレックスにも注目しました。たとえば、フロイトが提唱した「父親と息子の対立構造から来るもの=エディプス・コンプレックス」に対して、精神分析学者の古澤平作は「”完璧な母”ではない母、への憎しみと愛着、母の許しに対する罪悪感などの複合心性(コンプレックス)=アジャセ・コンプレックス」を提示して、異議を唱えたそうです。
「王舎城の悲劇」の物語の世界に引き込まれ、ことばにできない感情にゆさぶられている中、釈先生が講座の最後に仰った言葉が染み入りました。
「出会ってしまったらその前には戻れないような、そんな力が物語にはある。自分の為に用意されたと思う物語に出会ったときに、人は救われるのではないでしょうか」