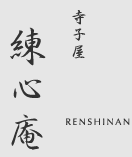2016/05/20 練心庵伝統芸能シリーズ ~練心庵落語会春席~
5月20日、皆様に伝統芸能をご紹介する、練心庵伝統芸能部の第一弾として、練心庵落語会春席が開催されたときのリポートです。 お馴染みの桂優々さんの落語に加え、落語作家のくまざわあかねさんと練心庵主宰釈徹宗の対談も行われました。
(記:納谷久美子)
インターネットとパソコンとスマートフォンの普及により、誰もが簡単に最新ニュースを手に入れられるようになった現代においても、面白い話を誰よりも早く入手し、「なあ、これ知ってるか。知らんやろ。教えたるわ。」と話して回る情報通がいますねえ。古典落語の時代にも、そんな情報通がいたようです。
今回の落語「あみだ池」には、そんな情報通が登場します。

「ほら、知らんかったやろ?せやから新聞を読めと言うとんねん!」
おお、学校の先生のよう。
(もっとも、当時の新聞ですから、おもしろおかしく書いた記事も多かったでしょうが。)
困ったことに、この情報通の人、ニュースの中にホラも混ぜて、相手が驚くのを楽しんでいるようです。騙されてくやしい主人公、同じホラ話を他の人にも聞かせて驚かせようとするのですが・・・
久々の落語会。
落語は桂優々さん、ゲストは落語作家のくまざわあかねさんでした。
え、「落語作家」?!
聞きなれない肩書きですよねえ。
落語は、昔からある「古典落語」だけでなく、現代になってから作られたものもたくさんあるのです。
専業の落語作家は、くまざわあかねさんと小佐田定雄さんのお2人だけなんだそうです。(くまざわあかねさんは小佐田定雄さんのお弟子さんでもあり奥さんでもあります。)
くまざわさんがおっしゃるには「落語作家は免許制ではありませんから、名乗ろうと思えば名乗れます。」とのことです。釈先生は「題名とあらすじとオチだけ残っている古典落語」の中身を創作したことがあるそうで、「ほな、名刺に落語作家て書こうかなあ~」などとおっしゃってました。おお!ええやないですか。

さて、その「古典落語」の舞台ですが、江戸時代だけとは限りません。明治・大正時代のものもあります。
聞いていて、
「おや?江戸じゃなくて東京って言うてるでえ?」
「ん?汽車?郵便局?」
などと思ったことはありませんか?
「古典落語」とは昭和10年ごろまでが舞台のものを言うそうです。
くまざわあかねさんは、落語の時代の生活を1か月間やってみたことがあるという、なんとも興味深い方です。あまり古すぎては資料がなくて困るので、江戸時代の生活ではなく、実際に当時を知る人に聞ける「昭和10年ごろ」の生活を再現してみたそうです。また、江戸時代の生活をするには、髪も結わないといけないなど、現代人にはあまりにも困難です。

家の中で電気製品を使わないだけではありません。外に出ても、「銀行はあるけどATMは無かったから、窓口でお金をおろす」「御堂筋線は開通してたから乗ってもよい」など、徹底して「昭和10年ごろ」の生活を体験。「あとで調べたら、当時もうエスカレーターがあったんですよ。つこたらよかったわあ」などとおっしゃっていました。階段しか使わなかったんですね。
その生活の様子を書いた本も出版されているので、興味をお持ちになった方は探してみてくださいね。