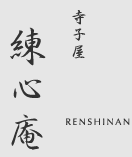2016/07/14 7月期 初歩からの宗教学講座
7月14日に行われた「7月期初歩からの宗教学講座」のリポートです。
(記:多谷ピノ)
今回の「初歩からの宗教学講座」、テーマは「キリスト教を学ぶ」でした。
日本のクリスチャンの人口は、100万人。人口の約1%です。クリスチャンでなければ結婚式のチャペルくらいでしか関係ないと思われがちなキリスト教ですが、「キリスト教を知らないと現代社会の落とし穴、苦悩が見えない」と釈先生は冒頭でいきなりおっしゃいました。
日本に土着していないと思われがちなキリスト教、実は、現代日本に浸透している教育や倫理観はキリスト教の影響を受けているのだそうです。また、民主主義や資本主義という枠組みは、キリスト教文化圏が鍛錬してきたものであり、キリスト教への理解なくては我々の社会はわからないとのことに、深く感じ入りました。
――――――――――――――
主の祈りと使徒信条
――――――――――――――
まずはキリスト教を信仰する上で欠かせない、「主の祈り」と「使徒信条」の解説から始まりました。「主の祈り」は、イエスが「このように祈りなさい」と言ったと聖書に書かれているもので、クリスチャンの祈りのベースとなるものです。
「アーメン」の説明を受けつつ、この「天におられるわたしたちの父よ」で始まる主の祈りを読み解いていきます。ここでのポイントは「わたしたちの罪をお許し下さい」と父なる神に許しを請いながら、「私たちも許します」と記されていること。神様に許されると同時にわたしたちも許す、というスタンスが、キリスト教の構造です。
そして「使徒信条」。
4世紀に完成した使徒信条は、異端とのせめぎあいの中で完成しました。クリスチャンは受洗のとき、この「使徒信条」に書かれていることをすべて信じているかどうかを確認されます。そこには、父なる神を信じているかどうか、イエス・キリストを信じているかどうか、など、クリスチャンが「信じるもの」について羅列されています。特に、イエス・キリストが死んでから三日後に蘇ったことを信じるかどうかが、クリスチャンにとって大事なポイントになります。
――――――――――――――
キリスト教の二軸構造
――――――――――――――
イエス・キリストに洗礼を授けた洗礼者ヨハネ。元々はユダヤ教の神官の家系だったようです。しかし、そこを飛び出し、出家者のような生活をし、「神の国は近づいた」と人々に説いて回っていたそうで、ユダヤ教の中ではマイノリティだったとのことでした。イエスも洗礼者ヨハネと同じく、当時のユダヤ教の中のひとつである、エッセネ派という修行僧のようなグループに属していたそうです。
キリスト教には「原罪」という独特の価値観があります。誰もが罪を背負った存在であるという罪の文化が、キリスト教文化圏を支えています。そして、その全人類が背負っている罪を償うために、イエス・キリストは十字架にかかったというわけです。イエスへの信仰を通して、人々は罪を償うルートが用意されました。それは他者への許しを生むのです。このことが人類へもたらした貢献は計り知れないと釈先生はおっしゃいました。
私は神に許されているのだから、私も隣の人を許すという、二軸構造がキリスト教にとって大事なポイントになります。他者を許すことによってのみ、神の愛が成り立ちます。どちらか欠けても成り立ちません。
――――――――――――――
Religion (レリジョン)の意味
――――――――――――――
明治期に「宗教」と翻訳された「レリジョン」という言葉は、元々は「もう一度関係を結びなおす」という意味だったそうです。そこからわかるように、キリスト教文化圏では宗教を、本来はダメになった神との関係を結びなおすことだと捉えるようです。
日本が考える「宗教」と「レリジョン」を同じように考えるとズレが乗じるのではないかとあらためて実感しました。そして、「キリスト教の理解なしに近代社会は成り立たない」とおっしゃった先生の冒頭の言葉も思い返しました。
講義はさらに続き、ダ・ヴィンチの『最後の晩餐』などキリスト教をモチーフにした絵画をスライドで見せていただくなど、多方面からキリスト教を解説していただきました。今回も盛りだくさんの内容で書ききれません!次回も引き続き、キリスト教について行われる予定だそうですので、どうぞお楽しみに!