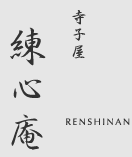2016/08/19 8月期「初歩からの宗教学講座」
8月19日に行われた「8月期初歩からの宗教学講座」のリポートです。
「キリスト教を学ぶ(その2)」と題された今回の講座。前回のおさらいから始まりました。前回に参加していなかった方はもちろん、前回も参加していた方も、キリスト教の簡単な概要を短い時間で振り返ることができ、安心して講座を受けることができました。
—————————–
行為と信仰
—————————–
講座の冒頭で、釈先生はキリスト教について、こう説明してくださいました。
「2000年ほど前にイスラエルで活躍したイエスという人物を通して神の愛を知る道、それがキリスト教です。」
「イエスという人物を通して」とおっしゃったように、キリスト教が普及したのはイエスの存命時ではなく、その昇天後でした。イエス自身はユダヤ民族に生まれ、ユダヤ教の新しい一派を作ったつもりだっただろうとのことです。
ユダヤ教という宗教は、行為を非常に重視します。日常において細かい決まり事があり、食べていいものいけないものや、安息日など、はっきり決められています。
一方のキリスト教は、戒律より内面の信仰を重んじます。「よこしまな目で他人の奥さんを見る」だけでもダメなのがキリスト教です。行為重視と内面重視。どちらを重視するかは、それぞれの宗教の性格の違いによります。
キリスト教には、「伝道こそ信仰のあかし」という思想があります。ユダヤ教徒として生まれ、ユダヤ教徒として死んでいったイエスの教えが広まったのは、ひとえに弟子たちの伝道のおかげです。イエスのことを厳しく批判していたパウロも、後にはクリスチャンになり、各地を伝道します。パウロはユダヤ人以外にも伝道を始め、その意味では、キリスト教はパウロから生まれたとも言えます。パウロは人々に、ユダヤ教の決まりは守らなくていい、大事なのは神だと伝道しました。こうして、信仰こそ正しいと認められる信仰義認や、律法からの解放が各地に広まっていったのです。
—————————–
宗教的逆説性
—————————–
「貧しいものこそ幸せである」という「平地の説教」の一節には、「悪人こそが救われる」という『歎異抄』の悪人正機と同じような宗教的逆説性が感じ取れます。
世俗をひっくり返す魅力をもった宗教は、宗教的逆説性を持ちます。この世俗と同じものを提示しては宗教の価値はありません。世間とは別の価値観だからこそ、社会では救われない人間が宗教で救われるのですから。ただ、だからこそ宗教は危ないとも言えます。社会とバッティングを起こすこともしばしばです。
迫害をうけている者よ、あなたこそが正しい道を歩いている、というキリスト教の理論は、「苦難の神義論」と呼ばれます。これと対極にあるのが「幸福の神義論」です。「おかげさま」に代表される思想です。
苦難の神義論を構築したキリスト教徒たちは、どんなジャングルの奥地でも踏み入って、伝道を続けました。迫害されて惨殺されても、いえ、むしろ、迫害されればされるほど、自分のしていることは正しいという神義論を突き詰められたのです。
—————————–
遠藤周作の『沈黙』
—————————–
日本人作家でクリスチャンである遠藤周作の代表作に、『沈黙』があります。スコセッシ監督による映画化も決定し、2017年に「沈黙-サイレンス-」の邦題で公開されるそうです。キリシタンの迫害の物語であるこの作品は、日本の宗教観とキリスト教のはざまで苦しんだ遠藤の叫びが込められている気がします。
島原の乱以後の長崎で、ポルトガル人司祭ロドリゴは、井上筑後守に棄教を迫られます。死ぬのも怖くないという決意で、伝道のため日本に来たロドリゴですが、数々の苦難を受ける中でひとつだけ疑問を持ちます。こんなに信仰篤い人々が苦しんでいるのに、神はなぜ沈黙しているのだろうか、という疑問です。先に棄教したフェレイラ司祭はロドリゴに、「この国は沼地だ」と言います。どんな木を植えても根は腐っていく。どんな木を植えてもダメなんだ、と。仲間の拷問に悩んだロドリゴは、ついに踏み絵を踏む決心をします。それでもなお沈黙する神に対し、ロドリゴは死を決意します。しかし、そこで初めて、ロドリゴに神の声が聞こえるのです。「踏め」と。「お前に踏まれるために私はいるのだ」と。
この作品によって、遠藤はかなり批判されたそうです。そんなのはキリスト教の神ではない、お前の神は浄土真宗か、と。
共に泣く神、父なる神でなく母なる神を描いた遠藤ですが、キリスト教の母性はキリスト教の中に内蔵されていると釈先生はおっしゃいました。宗教には様々な要素があり、その地域に合ったところが発達するのだと。
資本主義、民主主義の二本柱はキリスト教文化圏から生まれました。わたしたちが普段抱いている、宗教=信仰というイメージも、キリスト教の影響からです。現代社会はキリスト教の知識なしに語れない苦悩もわからないと言えるでしょう。これからも機会あるごとにキリスト教の話をする、と講義は締めくくられました。キリスト教を通して、信仰というものを深く考えた90分でした。
(記:多谷ピノ)