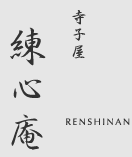2016/09/28 第1回「発掘!仏教埋蔵噺」
9月28日、桂文我師匠をお招きしまして第一回「発掘!仏教埋蔵噺」を開催しました。そのときの様子を参加者の久米秀慶さんがFacebookでリポートしてくだいました。
ご本人の許可を頂いてここに転載させていただきます。
皆様もどうぞ講座のご感想などお寄せください。
記念すべき第一回 発掘!仏教埋蔵噺
於 練心庵
桂文我師匠を招かれて
○仏教埋蔵噺~仏教系小噺いくつか
○その後落語二席
○最後に、釈先生と対談
二席の落語も、古い根多台本の中にある小噺から、ひとつの噺へ膨らませ構成、披露出来るものへ仕立て直された仏教落語。
埋蔵されている根多台本から、復活させるのは、文我師匠ならでは。
(枝雀独演会に弟子として全国各地同行されてた頃から、20年以上全国古本屋巡りに因る)
故桂米朝師は、芸人さんであって落語研究者という側面があり、その米朝師の研究家側面後を引き継ぐ人なく、それでは白羽の矢が立って文我さん文献研究を始める。
米朝師匠とのエピソードは、何度聞いても懐かしく嬉しい。
古い話しで、こんなのがあると、巡業先宿にて、紹介し出す米朝師匠。発掘好きだし、関心があるから、若手に伝える様子が、よく伝わる。
(大昔にあった街角の売声の形態模写もされてたな~おでん売りだったかな)
落語研究者・芸能研究者・民俗学者などの、研究者に対して、芸人側から見て、間違っているところ指摘出来る人が必要。芸人側からも文献研究する人が必要で、米朝師匠の後、誰もそんな能力がある噺家いないのが問題で、始めることに。
釈先生と文我師匠との対談。すべて書き起こしたいくらい勉強になったし、面白く聞かせて頂いた。
その対談にて、師匠質問「地蔵さんとは?」
大地の仏であり、大乗仏教中国で、道教と引っ付き、辻・境界を守る仏であり、特徴的な事は、衆生の苦しみを身代わりされる、身代わり地蔵もあると、解説される釈先生。
身代わりで、思い出した師匠が、小さな時、身代わり地蔵が近所にあり、歯痛を身代わり地蔵にお参りした。近所のお婆さんも、歯痛で、その地蔵さんにお参り、翌日そのお地蔵さんの頬にサロンパスが貼られていた。
地域でちょっとした騒動になったが、お参りしたお婆さんが貼ったものだったというエピソード。
この地蔵さんとお婆さんのエピソードが、素敵な話しでした。畏るべし松阪。宗教感覚・死生観豊かな地域ですね。
あとは、遅筆なため伝えきれません。
詳しくは、第二回埋蔵噺ご参加され体験下さい>_<
(記:久米秀慶さん)