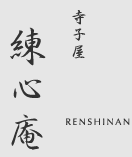2016/12/16 第2回 「発掘!仏教埋蔵噺」

12月16日、桂文我師匠をお招きしまして「発掘!仏教埋蔵噺」を開催しました。そのときの様子を参加者の久米秀慶さんがFacebookでリポートしてくだいました。ご本人の許可を頂いてここに転載させていただきます。皆様もどうぞ講座のご感想などお寄せください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第二回 発掘!仏教埋蔵噺 於 練心庵 桂文我師匠
比較宗教学的にも、貴重な根多『三年酒』
釈先生も生で聞きたいとリクエストされていた噺(ご当地ネタ池田が舞台の噺)
以前米朝師匠がされていて、現在は文我さんと桂宗助さんお二人ぐらいしかされていないという事で、全く知らない噺でしたので、埋没されず聞けてとても良かった。
桂米朝師匠も現役時「あっちやこっちでやれるといぅ噺でもございません。といぅのが、ケッタイな噺でして、坊さんボロクソに言ぃまんねやなぁ、この噺わ」と話されている。
少しだけ落語三年酒(さんねんしゅ)を紹介しますと
〈落語冒頭〉キリスト教の弾圧という事でそれで、人別というものが出来た。人別帳を預かる寺には逆らえない。神道講釈に凝っている又七(又はん)という男が酒を飲み過ぎため死んでしまった。本人の希望通りに神道で葬式を出そうとしたが、和尚が承知しない。
そこで和尚の説得に向かうのがオネオネの佐助・高慢の幸兵衛・コツキの源兵衛という三人組。(さてどうなりますやら。続きは落語会でお楽しみ下さい)
オネオネの佐助とは、おねおねおねおねと前置きの長い話をし、相手がしびれを切らせ説得しよう、高慢の幸兵衛とは、高慢上から目線で説得しよう、コツキの源兵衛とは、最後の手段こついて腕力で説得しようとする個性あるキャラクター
曽根駅が、帰りには「そね」から「おね」(笑)に思えるくらい愉快な登場人物。
そんなおねおね話す人物は、落語界・大学の先生にもいますか?「(師匠と釈先生)いますね」(笑)

文我師匠と釈先生の対談にて
落語まくらの話されていた文我師匠幼少期の近所の教会の牧師さんハナゾノさんとのエピソード。子供向けの集会をされていた教会。綺麗なカードをもらうのがお目当て。とある日、近くの川へ洗礼を見学する日があり、見に行った。何も説明されず、牧師さんがいきなり「どぼんと」信者さんを仰向けに川に浸けられる。以降二度と行かなくなった。。(笑)
(釈先生より)
川の中で洗礼式をされた全身洗礼なので、バプテスト派ですね。パプテスト派は、洗礼せんれいといわず、しんれいという。
教会によっては大きな浴槽のようなものがあって全身で受ける形。
カトリックには幼児洗礼がある。カトリックは、生まれたら洗礼を受けるので、その地域の人はその教会に属す、日本の檀家制度に似ていますね。
プロテスタントは、信仰を持って受けるのが本物とし、成人してから、洗礼を受け、パレスチナ地方でやっていた川で受けるような全身を浸すスタイルを大切にする。
(文我師匠より)
米朝師匠の師匠四代目桂米團治は、洗礼を三回受けはった
米朝師匠が「なんで3回も受けはったんですかー」と尋ねられると
「気持ちええさかいねー」(笑)
受けさす方も、受けさす方ですね(笑)
(釈先生より)
神道と仏教の話題
神道も外来の神といえる。新モンゴロイド系北方系の
それまでは、土着の信仰が各所に点在していた。
仏教がやってきたことで各地域・各地域の信仰が体型化。
日本の場合は、双子の宗教といえる。
五木寛之さんより教えて頂いた事ですが、
一時、外来種で悪評高かったセイタカワダチソウが、
今では、小さくなって可憐かれんになっているという。
あまり背が高くない(笑)あわもあまりたたない(笑)
文我師匠「ただの草ソウですね(笑)」
変質するものが、土着し、土着しないものは、定着しない。
日本に順応し小型化したという話。
神道だから、火葬しなくて、助かったというのが話の根幹ポイントですが、
神道は土葬、仏教は火葬という事に噺の中ではなってますが、
そこから世界の土葬火葬について
両墓制 サンマイヒジリ 三昧聖
文我師匠も三昧聖のようなそのような方おられました、思い出しましたと。
前回も、地蔵さまの話しも印象深いが、改めて文我師匠は小さい頃から宗教体験が、豊富な方だと驚く。またそんなエピソードを踏まえながら、仏教落語・宗教文化の落語を聞くのは至福でした。
対談休憩をはさみ、二席目お楽しみは、
季節感ある情景が浮かぶ『二番煎じ』
対談でも話が出ましたが、文我師匠と年齢が近く親しい関係の桂宗助師匠。その高座名は「二番煎じ」の登場人物「宗助」から。三年酒は、宗助さんが昔からやっていて文我師匠もされるように。

〈落語冒頭〉町内に一軒「番小屋」という小屋をしつらえまして、夜になりますと火の用心、火の回りということで、町内をこぉ回って火の用心をするわけでございます。
「火の元用心、火の用心、さっしゃりましょう」文我師匠の威勢のいい掛け声!
地域の一消防団員ですので、年末夜警に向けこちらも味わい深く聞かせて頂きました。次回3月も楽しみであります。
※追伸
糸魚川火災にて、たいへんな被害に遭われた被災された方々へお見舞い申し上げます。
(記:久米秀慶さん)